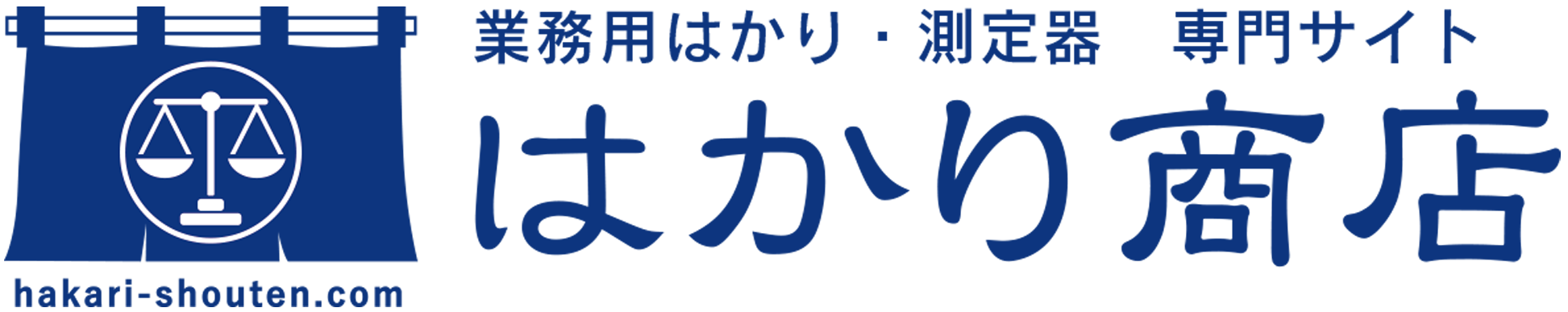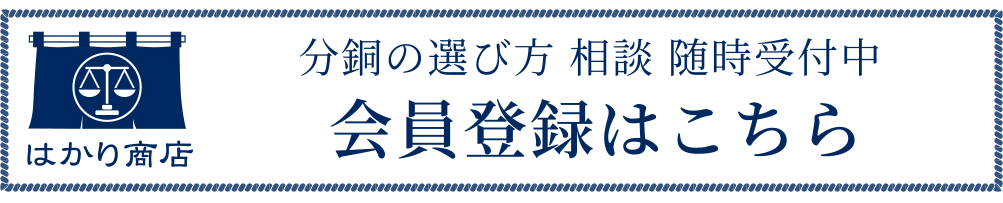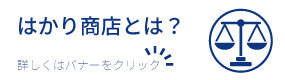-
はかり
-
分銅
-
温度計・湿度計
-
タイマー
-
長さ測定器
-
濃度・環境測定
-
色々な計測器
-
レベル・勾配測定
-
オプション
- ホーム
- はかりの基礎知識
はかりの基礎知識HAKARI KNOW HOW
分銅の選び方
お客様がご使用になられているはかりが、正しいかどうかを調べてみませんか。
狂いはいつ生じるかわかりません。長期間の使用・置き場所や使用場所の移動・汚れなどで、
重さ表示にずれが発生するかもしれません。
そこで、正確に計量できているかを点検するために分銅を用意しましょう。
点検や検査の種類には、主に下記のようなものがあります。
| 01 日常点検 | ご使用前に、設置状況(汚れ・水平など)をご確認いただき、 普段測定している重量の分銅を載せ、重量表示を確認します。 分銅を下した後、ゼロに戻るかも確認してください。 |
|---|---|
| 02 定期点検 | 日常点検に加え、秤量や秤量の1/2の分銅を載せて重量表示を確認します。 ゼロ点を含め4点以上のポイントで確認して頂くことをお勧めいたします。 また、偏置(四隅)に秤量の1/3の分銅を載せ重量表示を確認します。 |
| 03 定期検査 | 取引や証明に使用するはかりは、特定計量器(検定付)を使用し、 公的機関または計量士により2年に一度の公的検査を受けなければなりません。 取引や証明以外でご使用になるはかりは、計量士または、はかりの修理や校正を 行っている事業者等外部機関での検査をお勧めいたします。 |
お客様(はかりの使用担当者)が行う日常点検・定期点検に必要な分銅の選び方をご説明いたします。
くわしい点検方法の説明はこちら→ 点検・校正の方法へリンク
大切な準備
点検するはかりの秤量(計量できる最大値)と目量(計量できる最小値)を調べておきます。
秤量と目量は、はかりの側面や裏面等に取り付けられている銘板、または取扱説明書等で
確認できます。また、点検するはかりで普段計量している重さも調べておきます。
分銅を選ぶポイント分銅を選ぶポイントは4つあります。
- 等級class
- 質量weight
- 形状shapes
- 材質material
例として、下記のはかりの点検に必要な分銅を考えていきましょう。
| 例上皿電子はかり | ひょう量 | 6000g |
|---|---|---|
| 目量 | 1g | |
| ふだん計量している重さ | 2000g |
はかりの精度等級を調べます。
はかりの精度等級を調べることで、どの程度まで精度の高い点検が必要なのかがわかります。
はかりの目量の数を計算し、はかりの精度等級表により、精度等級と最小測定量を決定しましょう。
「目量の数」は、ひょう量/目量を計算します
| 目量の数の例 | ひょう量6000g/目量1gの場合 ...... 6000÷1=6000 目量が1gで、目量の数は6000なので、精度等級は3級となります。 |
|---|
また、下の表からわかるように、精度等級が3級/目量が1gのはかりの最小測定量は20×目量(e)なので
最小測定量は20gであることがわかります。
はかりの精度等級表(現行の計量法)
| 精度等級 | 目量 | 目量の数 | 最小測定量 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 0.01g以上 | 50,000以上 | 100e |
| 2級 | 0.01g以上0.05g以下 | 100以上100,000以下 | 20e |
| 0.1g以上 | 5000以上100,000以下 | 50e | |
| 3級 | 0.1g以上2g以下 | 100以上10,000以下 | 20e |
| 5g以上 | 500以上10,000以下 | 20e | |
| 4※級 | 1g以上5g以下 | 100以上1,000以下 | 10e |
| 4級 | 5g以上 | 100以上1,000以下 | 10e |
次に、下の表から、はかりの最大許容誤差を確認します。
はかりの最大許容誤差とは、法規で許される範囲のはかりの誤差のことです。
はかりの精度等級表(現行の計量法)
| 精度等級 | 目量で表した荷重 | ||
|---|---|---|---|
| 1級 | 0以上~50000以下 | 50000より上~200000以下 | 200001以上 |
| 2級 | 0以上~5000以下 | 5000より上~20000以下 | 20000より上~100000以下 |
| 3級 | 0以上~500以下 | 500より上~2000以下 | 2000より上~10000以下 |
| 4※級・4級 | 0以上~50以下 | 50より上~200以下 | 200より上~1000以下 |
| 最大許容誤差 | ±0.5 × 目量 | ±1.0 × 目量 | ±1.5 × 目量 |
| 精度等級3級のはかりの最大許容誤差は、 | 500g以下のとき | ±0.5g |
|---|---|---|
| 500gより上~2000g以下のとき | ±1.0g | |
| 2000gより上~10000g以下のとき | ±1.5g |
実際に点検を行い、これより大きい誤差がでたという結果に なると、技術員による点検・検査が必要です。
次に、使用する分銅の質量を決めます。
| 例上皿電子はかり | ひょう量 | 6000g |
|---|---|---|
| 目量 | 1g | |
| ふだん計量している重さ | 2000g |
| 日常点検 | ふだん計量する重さが2000gなので、 必要な分銅は 2kg × 1個 となります。 |
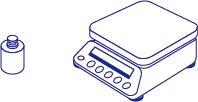 |
|
|---|---|---|---|
| 定期点検 | はかるポイントは 0g(0点確認) 20g(最小測定量) 2000g(ひょう量の1/3) 3000g(ひょう量の1/2) 6000g(ひょう量) |
必要な分銅は 20g×1個 1kg×2個 2kg×2個 となります。 |
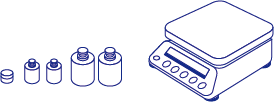 |
次に、分銅の等級を決めます。
等級は、分銅の最大許容誤差表から決定します。
分銅の最大許容誤差とは、分銅のもつ質量の誤差のことです。
〇級という表現がされており、クラスが上がると精度があがります。
最大許容誤差の表を参照しながら計算し、分銅のもつ誤差を許容範囲内におさめる必要があります。
分銅の最大許容誤差は目量の±1/3以下ということが決まっています。
| 例上皿電子はかり | ひょう量 | 6000g |
|---|---|---|
| 目量 | 1g | |
| ふだん計量している重さ | 2000g |
(例)のはかりの目量は1gなので、最大許容誤差は333mgとなります。
分銅の等級と最大許容誤差*JIS B 7609による
| 表す量 | E2級 | F1級(特級) | F2級(1級) | M1級(2級) | M2級(3級) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20kg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1000mg | ±3000mg |
| 10kg | ±16mg | ±50mg | ±150mg | ±500mg | ±1500mg |
| 5kg | ±8.0mg | ±25mg | ±75mg | ±250mg | ±750mg |
| 2kg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg |
| 1kg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±15mg | ±50mg | ±150mg |
| 500g | ±0.8mg | ±2.5mg | ±7.5mg | ±25mg | ±75mg |
| 200g | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
| 100g | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.5mg | ±5mg | ±15mg |
| 50g | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg |
| 20g | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.80mg | ±2.5mg | ±8mg |
| 10g | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.60mg | ±2.0mg | ±6mg |
| 5g | ±0.05mg | ±0.15mg | ±0.50mg | ±1.5mg | ±5mg |
| 2g | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.40mg | ±1.2mg | ±4mg |
| 1g | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3mg |
| 500mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg | ±0.80mg | ±2.5mg |
| 200mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg | ±0.60mg | ±2.0mg |
| 100mg | ±0.016mg | ±0.050mg | ±0.15mg | ±0.50mg | ±1.5mg |
| 50mg | ±0.012mg | ±0.040mg | ±0.12mg | ±0.40mg | ±1.2mg |
| 20mg | ±0.010mg | ±0.030mg | ±0.10mg | ±0.30mg | ±0.90mg |
| 10mg | ±0008mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg | ±0.75mg |
| 5mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | - | - |
| 2mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | - | - |
| 1mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.060mg | - | - |
例えば目量が0.1gの場合、最大許容誤差はその1/3の±33mg以下の分銅を選びます。
組み合わせる場合は、それぞれの分銅の最大許容誤差も合計して考える必要があります。
表を参照して考えます。
20gは1個しか載せないので、
M2級 (M2級20gの許容誤差は±8mg)
2kgと1kgの分銅については、ひょう量6000gの点検で、
すべてをのせることになります。
よって、2kg×2個と、1kg×2個をすべて合わせても
誤差が許容範囲内になる分銅を選ぶ必要があります。
例として、M1級とM2級で考えてみます。
| M2級の場合 | 2kgの最大許容誤差は±300mg、1kgの最大許容誤差は±150mgなので ・2kg 300mg × 2個 = 600mg ・1kg 150mg × 2個 = 300mg あわせて±900mgとなり、最大許容誤差を超えてしまいます。 |
|---|---|
| M1級の場合 | 2kgの最大許容誤差は±100mg、1kgの最大許容誤差は±50mgなので ・2kg 100mg × 2個 = 200mg ・1kg 50mg × 2個 = 100mg あわせて±300mgとなり、最大許容誤差の範囲内におさめることができます。 |
よって、この場合は20gはM2級で、1kg と 2kgはM1級となります。
分銅の形状を決めます。
 |
円筒分銅一般的に広く知られている分銅です。 |
|---|---|
 |
円盤分銅ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。 |
 |
増おもり型分銅吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使います。 |
 |
枕型分銅ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 |
 |
板状分銅小質量の分銅で、はかりの感度確認や、精密なはかりの点検に使用されます。 |
分銅の材質を決めます。
材質を決定するポイントは耐久性とコストです。
耐久性を選ぶならステンレス製が良いですが、コストを考えるとそれ以外という選択肢もあります。
-
・ステンレス製
質量の変化が少なく、耐久性が高い。
-
・黄銅クロムメッキ製
メッキで表面処理がされているため、腐食する可能性がある。ステンレス製よりコストが低い。
-
・鋳鉄製
塗装がされているので剥げることがあるが、ステンレス製よりコストが低い。
-
・洋銀製
板状分銅に使われている。ステンレス製より等級は低いがローコスト。
はかり商店の「等級」別 分銅はこちらです!
はかり商店の「質量」別 分銅はこちらです!
はかり商店の「形状」別 分銅はこちらです!
はかり商店の「材質」別 分銅はこちらです!
業務用はかり専門サイト

|
はかり商店では、点検・校正についての アドバイスをおこなっています。 ぜひお気軽にご相談ください。 |
|---|
-
点検・校正の方は...
はかりの豆知識:点検・校正の方法 -
分銅の選定に迷われている方は...
点検・校正問い合わせフォーム